
集中治療室で友だちから、「あなたはピルを過剰摂取したのよ」と言われた時、私はぼうっとしながら尋ねた。「避妊用のピルのこと?」
私が寮の部屋の外にある冷水機の前で実際に飲んだのは、2瓶分の抗うつ剤だった。一日中、アルコールも飲んでいたので、完全に命取りな組み合わせだ。
もちろん、酔ったはずみではなかった。
その3カ月前、私は、別の医療施設、つまり、精神病院の患者だった。親友のデニスがクリスマスに自殺した。彼女の葬儀の数日後、私も死にたいと母に言った。彼女の死に果たした自分の役割を思うと、自分を許せなかった。デニスを救えなかっただけではない。デニスが自殺を思い立ったのは私のせいだと、かなりの確信も持っている。
思春期を迎えてからというもの、自殺は、ずっと私のアイデンティティの一部だった。私はたぶん、大うつ病性障害を発症していたのだが、そうは診断されず、治療を受けないまま5年が過ぎていた。振り返ると、10代の頃の自分は魅力的で利発な人気者だったと言えるだろう。だが日記帳には、自殺願望や自己嫌悪に満ちた言葉があちこちに書き込まれている。
それに、私とデニスが同時に妊娠に怯えていたとき(デニスにとっては初めての、私にとっては二度目のセックスだった)、私が考えた「解決策」は、家族の留守中に、デニスの家のガレージにある彼女の赤いフォード車で排気ガス自殺をすることだった(たぶん、無防備なセックスをしたストレスのせいで生理が遅れ、長い時間2人で一緒に過ごしていたので、同じ周期になっていたのだろう)。
だが、最初に自殺を試みたのは私のほうだった。弟の処方薬を16錠飲み、涙に濡れた感傷的な短い遺書を書き、デニスに電話して、今からすることを伝えた。もちろん、デニスは駆け付け、私の母に話した。母は中毒情報センターに電話をかけた。デニスと弟が催吐薬を買いに薬局に急いでいるあいだ、母は家に残って私を見張っていた。
数々のドラマがあり、何度も嘔吐して、大いに注目を集めた。注目こそ、私が求めていたものだと思う。それは助けてほしいという叫びであって、本気で自殺しようとしたわけではなかった。そして、心の叫びに、催吐薬と家庭医、そして最終的にはセラピストが応えてくれた。
それでも、私の自殺願望は薄れなかった。大学1年生の作文のレポートでは、簡単さや費用、成功率に基づいて様々な自殺方法を評価した(この論文で「A」評価をもらったが、心配した教授に付き添われて診察も受けた)。
そして、おそらくそのレポートが理由のひとつとなって、私は、あの言葉を自信たっぷりに言ってしまったのだ。その後何十年も私をひどく苦しめることになったあの言葉を。
「アスピリンじゃ死ねないんだよ、デニス」
だがデニスは、そのアスピリンのせいで死んだ。以来、私は罪悪感を抱きながら生きてきた。

あの日はクリスマスだった。デニスは、大学の1学期が終わって家に戻っていた。常に成績優秀だったデニスはアイオワ大学に進学し、私は地元のニューメキシコ大学に入っていた。私たちの1学期は、かなり違った。私は机にかじりついてオールAの成績を取った。一方のデニスは、遠く離れた故郷にいる厳格な父親のしつけの手もおよばず、大半の新入生と同じく、新たに得た自由を満喫していた。
デニスはパーティー三昧の日々を送り、新しい友だちを作って、新しい彼氏を見つけた。だが、成績は下がり、単位を落としかけていた。冬休みに家に戻って、落第しそうだと父親に報告するのを恐れていた。その一方で、彼氏のトッドと車で学校に戻るのをとりわけ楽しみにしていた。トッドはアルバカーキまで車を走らせ、新しい彼女であるデニスの家族に会う計画を立てていたのだ(トッドは実際にアルバカーキまで来てデニスの家族に会ったが、それは、デニスの葬儀だった)。
クリスマス休暇は、私たちの誰にとってもすばらしいものとはいえなかった。私の両親は離婚し、母と弟たちは安アパートに引っ越していた。父は、近くの「ディスコ」のビルで、独身男性向けの部屋を借りていた。私は家族全員と折り合いが悪く、初めてアパートを借りていたが、新学期に備えて1月にニューメキシコ大学の寮に移るのを心待ちにしていた。
クリスマスイブは、デニスが家族と出かけていたので、戸口にプレゼントを置いてきた。季節限定でバイトしていた店の、グルメ向けポップコーンと、シャネルのマニキュアがプレゼントだった(デニスは自分でマニキュアを塗るのが大好きだった)。デニスはもっと気の利いたプレゼントをくれたはずだが、正直に言うと、何をもらったのかは覚えていない。お礼の電話を掛けると、デニスは不機嫌そうだった。トッドと車で学校に戻るのを父親に禁じられ、リクエストしていたプレゼント(ある歌手のデビューアルバム)ももらえなくてがっかりしていたのだ。
アスピリンを大量に飲んだとデニスに言われ、その効き目について軽はずみな返事をしたのは、そのときだった。実のところ、いらついていたのだ。デニスには彼氏がいて、両親のいる家庭もあり、いかにも中流階級らしい家で、戻ることができる自分の寝室がある。大学の授業料を払うために、くだらないアルバイトをする必要もない。
だから、デニスの話を真剣に受け止めなかった。自殺の方法に関する私のレポートでも、アスピリンは触れられていなかった。効き目が少しあったとしても、眠れば効き目が切れて、たぶん幸せな結果になるとさえ思っていた。父親は成績のことをもっと大目に見てくれるようになり、彼氏と車で学校に戻るのを許すだろう、と。
昼も夜もずっとデニスに電話をかけ直そうとしたが、いつも話し中だった(当時は携帯電話などない時代で、デニスの家族は通話中着信サービスを利用していなかった)。家に立ち寄るべきだという考えが頭を離れなかった。何にしても、デニスは、私が立ち寄るのを期待しているだろう。2年前、私が中途半端な自殺未遂をした際に、デニスはそうしてくれたのだから。
だが、私はデニスの家に行かなかった。最後にもう一度電話を掛けてから(まだ話し中だった)、ベッドに入った。翌日はバイトに行かなければならなかったし、翌日の夜は冬休みを祝うパーティーを私のアパートで開くはずだったので、その準備もしなければならなかった。凝ったことは何もしないつもりだったが、法的に酒を買える年齢の友達との調整が必要だった。
翌日も、デニスからの連絡はなかった。でも私は、心の奥底ではほっとしていたと思う。ポップコーン店では気が狂いそうなくらい忙しかったからだ。パーティーの前には連絡がとれると思っていた。案の定、家に帰るとすぐに電話が鳴った。しかし、掛けてきたのはデニスではなく、デニスの妹だった。「すぐに来てくれる?」。その声は震えていた。私は突然、寒気がして、少し怖くなった。1分で行くと告げると、デニスの父親が内線電話を取り、もっと差し迫った調子で娘の頼みを繰り返した。「すぐに来てくれ。今すぐにだ」
デニスが親と口をきかないので、仲を取り持たないといけないのか、あるいは、デニスが病気で、私に会いたがっているのだと思った。すぐに別の友だちに電話し、パーティーは中止だと皆に伝えるように言い、車に乗り込んでデニスの家に向かった。台所で人が動いているのが見え、少しほっとした。デニスの父親がドアを開け、中に引き入れた。私たちは廊下を進み、デニスの部屋に向かうと思ったのだが、彼の書斎に引っ張り込まれた。理由を聞く間もなく、強く抱きしめられ、「デニスが死んだんだ」と言われた。
緊急治療室の看護師であるデニスの母親も、娘の容態が深刻であることに気付いていなかった。12月26日未明にデニスを病院に連れて行った際、母親は夫に対して、先に帰って、計画通りにほかの子どもたちをスキーに連れて行くよう言った。彼らは何も知らずに帰宅したのだが、そのときすでにデニスはすでに亡くなっていたのだ。
私は、共通の友人といっしょにアパートに戻った。一睡もせずに、私のせいじゃない、と自分に言い聞かせた。自分でも、そう信じかけていた。翌朝、友人全員に電話してデニスの死を知らせた。ここで、恥ずかしく思うことがもう一つある。速報ニュースを「独占」した記者のように、この爆弾発言をすることに刺激を感じていたのだ。
電話を掛け終わると、さらに気分が悪くなった。デニスの父親に、自殺だったことは伏せておくよう頼まれたが、ほとんどの友だちはショックが大きすぎて質問してこなかった。アルバカーキは小さな町だ。1日も経たないうちに誰もが真実を知った。デニスがアスピリンを過剰摂取したということを。
でも私から見れば、彼らは真実の半分しか知らなかった。私の自殺願望に影響されて、自傷行為が「解決策」になるとデニスは考えたのだ。本気で死ぬつもりはなかった、と私は今、確信している。実質的には私がデニスを殺したのだと思った。「武器」を与えておいて、デニスがそれを使おうと決めたときに行動しなかったからだ。
10代の若者は、自分と同じ10代の若者を追悼するときには、たがが外れたかのように大げさに悲しむものだ。特にはっきりと覚えているのは、デニスと対面する前に、自分が葬儀場の前の芝生の上で声を出して泣いていたことだ。実は、数カ月前に、その葬儀場を訪れたことがあった。そこで働く高校時代の友人を説き伏せて、夜、葬儀場を閉めた後に、遺体を見せてもらったのだ(死に対する私の強いこだわりはとどまるところを知らなかった)。
今度は、故人となったデニスと対面するために再びその葬儀場に来ていた。友人はその午後も働いていて、茶色のスーツ姿で、同情するような表情を浮かべながら私を抱きしめた。目には涙が浮かんでいた。故人が知り合いというケースは、そのときが初めてだったのだろうか? 葬儀場で防腐処置をされているのがデニスだと、彼はいつ知ったのだろう? デニスの家族が棺を選ぶのを手伝ったのだろうか?
愛する者の遺体を見るのは、かなり恐ろしい体験だ。死んだのは自分のせいだと感じている場合は、なおさらだ。ようやく勇気を振り絞って棺に近づくと、生きていたときと変わらないデニスの姿に、思わず息を飲んだ。デニスは、お気に入りの毛羽だったセーターと、クリスマスプレゼントだった新しいジーンズを着せられていた。髪は整えられ、爪には深紅のマニキュアが施されていた。私がクリスマスにプレゼントしたシャネルのマニキュアだ。そばにいたデニスの妹が、服といっしょに新しいマニキュアを葬儀屋に渡したと説明してくれた。私は腕を伸ばしてデニスの手に触れたが、その冷たい感触にギョッとして後ずさりした。そして初めて実感した。デニスは死んでしまったのだ、と。
私はずっとデニスの家族とともに座り、デニスの妹たちの手をしっかりと握りながら、いっしょにすすり泣いた。だが、彼女たちは、いちばんの友でありお手本でもあった姉のために泣いていたが、私の悲しみは、罪悪感によって複雑なものになっていた。自分が欺瞞に満ちていて、その場にいる権利がなく、ましてやデニスの家族といっしょに座る権利などないように感じられた。
私は食べるのをやめた。デニスが食べられないなら、自分も食べないつもりだった。思いを誰にも話せなかったので、かわりに自分の部屋をめちゃくちゃにした。壊れなかったものを母が段ボールに詰めてくれて、私は母のところに引っ越した。そして葬儀の数日後、母の薬棚にある処方薬をすべて飲み込んだ。だが、すぐに薬を吐き出した。少しだけ正気に戻り、自分が味わっている苦悩を母に経験させたくないと思ったからだ。ただ、筋の通った自殺の計画を立てるには頭が混乱しすぎていたというのも本当だ。
翌日、母は精神科医に私を連れて行った。精神科医は、死んではいけない、すぐに入院するべきだと言った。その後の数週間、私にとって刑務所も同然となる場所に直ちに行きなさい、というのだ。母はそのまま私を精神病院に連れて行き、後で荷物を持ってきてくれた。恐ろしかったが、入院させられるのは当然だとも感じた。
精神病院では安心できた。初めてそこで、抗うつ剤を処方された。外来患者であれば適切な投薬量がわからず量を控えなければならないところだが、入院患者だったので、かなりの高用量だった。最初のうちは、私を閉じ込めているブル先生と精神科の看護師ドナに腹を立てていた。二人には毎日、長時間のセラピーセッションで会った。グループセラピーやアートセラピー、心理劇療法もあった。部屋ではプライバシーがなく、看護師が昼も夜も、定期的に様子を見に来た。よく眠ったが、食事はほとんど口にしなかった。
過去の出来事から、私は大うつ病性障害と診断された。今もまだ、その治療を受けている。抗うつ剤を飲むと、人間として再び機能しているように感じられた。1月が終わる頃には、担当の精神科医に、春から始まる新学期に備えて寮に移ってもいいとの許可を得た。それでも、週に数回、セラピーを受けに行き、薬物療法の経過を綿密に観察された。朝早くの授業は出席を控えなければならなかった。薬の鎮静効果が強く、夜には10時間以上眠っていたのだ。
私はなんとかルームメートおよびその友人グループと良い友だちになり、しょっちゅうつき合うようになった(友だちがアスレティックトレーナーを目指して勉強中だったので、運動部員が集まるパーティーにはすべて参加するようになった)。酒をがぶ飲みし、そのせいでひどい二日酔いになった。処方されている薬は、アルコールとの飲み合わせが良くなかった。だが、精神的な面では、気分が良くなり始めていた。春休みには、皆で車で旅行にも出かけた。
だが、自殺傾向がある人にとっては、「回復」するのは危険な場合がある。行動意欲が自殺につながってしまう場合があるからだ。また、春も危ないとされる。自殺はたいてい冬休みに発生するというのは、根拠のない話なのだ(デニスは明らかに例外だ)。実際には、自殺率は4月に急上昇することが多い。詩人のT・S・エリオットが「4月は最も残酷な月」と書いたのは正しかった。
その日は、ニューメキシコ大学で毎年開催されるスプリングフェスタの日だった。私は、ほかの数千人の学生と共に、日光浴をして1日を過ごした。何時間も酒を飲み続けてすっかり酔っ払っていた私は、寮の部屋の外にある冷水機で、抗うつ剤をひとつかみ飲んだ。完璧なタイミングを選んでいた。どちらの処方薬も最近調合してもらったばかりで、瓶にたっぷり入っていた。かかりつけの精神科医は、ようやく私を信頼し、1週間分ではなく1カ月分の薬を処方してくれるようになっていたのだ。
その後のことはほとんど記憶にない。誰かが私を見つけてルームメートに知らせ、ルームメートとその友だちが急いで私を大学病院に連れて行った。鼻にチューブを挿入しようとした医師に向かって、私が叫び声を上げて悪態を付いたらしいのだが、待合室でその声が聞こえたという話だ。胃洗浄された後、薬物を吸着させるために活性炭を投与された。あいにく、私はかなりうまくやったので、医師のもくろみ通りにはならなかった。私はあっという間に昏睡状態に陥った。
後でわかったことだが、私は間一髪のところを友人に病院に連れて行かれたのだった。3日間昏睡状態が続き、心配な発作が数回起きた後、集中治療室で意識を取り戻した。その前の1週間の記憶はほとんどなかった。大学警察は私の車を見つけるのに5日かかった。駐めた場所がわからなかったからだ。
普通の病室に移れるくらい十分に回復すると、私は再び日記を書き始めた。病院で初めて書いた、4月20日付けの書き込みが残っている。
そういうわけで、私は生きている。書くのは大変――腕に点滴をしているから。それに、真面目なことを書く気分じゃない。記憶がはっきりしてなくてよかったと思う。でも、人生って、そういうものなのだろう。笑える。人生って何だっけ? 私は死にかけた。奇妙すぎる。なぜ私は目覚めたのか? 死んでいたら、傷ついたりしないのに。他の人が自殺を……そして私を、怖がらないでほしいと思う。
何が起きたのかをたくさんの人が知ったため、私は動揺してしまった。私は、アメフトチームのほぼ全員がサインしたお見舞いのカードをもらった。(病院がキャンパスの向かいにあったので)見舞いに来てくれた者もいたが、いつも気まずかった。エチケットの本には、こういう場合の会話については書かれていない。いちばん親しい友人といっしょにいるときには、笑うことができた(友人クリスティーの父親は、私のことを心配して、飛行機で国を横断して彼女を大学から連れてきてくれた)。それに、記憶がはっきりしていなかったので、自殺について話すのを避ける良い言い訳になった。
その話題を避けなかった人もいた。たとえば、何年も前からたまに通っていたルーテル教会の牧師だ。今思うと、見舞いに来たときに言われた言葉に腹が立つのだが、当時の私は弱っていて、もちろん、その場を立ち去れる状態でもなかった。「神に背いた」と言われただけでなく、「どれほど家族を傷つけるか考えない自分勝手な人間だ」と非難されたのだ(こう叱られたのは、それが最後ではなかった。医師たちでさえ、私を厳しく非難した。メンタルヘルスに関する人々の無知と思いやりのなさは驚くほどだ)。
一方、デニスの父親は、私の罪を許してくれた。デニスを救おうとしなかったことをついに打ち明けたのだが、彼は病室まで来て、私のせいではないと言ってくれた。悲しみに暮れる父親なりの「答え」探しのなかで、彼は私がデニスに書いたメモや手紙をすべて読んでいたので、私が自殺にどれほど執着しているのか理解していた。デニスのように死んでほしくない、と彼は語った。
私たちはしばらく親しい関係でいたが、そのうち、つらすぎてデニスの家族と顔を合わせられなくなった。罪悪感と悲しみを切り離すことができなかった。愛する者が自殺した人たちの多くは、同じような苦しみを味わっているのだと思う。
今でもまだ、デニスの死は自殺の真似事だったもので、それが真似事では済まなくなったのだと私は思っている。デニスのほうが私より精神的に健全だった。私の間違った「解決策」を借りさえしなければ、自分の問題にうまく対応できたはずだと思う。
やっと退院の日を迎えると(肺炎にも罹っていたので、回復が遅れたのだ)、私は精神病院に戻った。そして、もう一度自殺を試みた後、またそこに舞い戻った。何年もセラピーを受け、抗うつ剤と抗不安薬の量を常に調整して、ようやく、自殺をけしかける自分の声が聞こえなくなった。というか、少なくともその声は、もっとかぼそくなって遠のき、誘惑が薄れている。
いまの私は幸運だ。すばらしい結婚生活を送り、私を愛し理解してくれる家族と友人がいる。刺激的で充実した仕事があり、すばらしい精神科医もいる。
親友の死に対する罪悪感には、まだとらわれている。でも、もし私が自殺したら、愛する者たちに同じ思いをさせることになることは理解している。たぶん、後に残された者はみな、自分にはできることがあった、すべきことがあった、と思い込むのではないだろうか――私ほどではないにしても。しかし私はうつ病を患っているので、これからも暗黒の日々は来るだろう。悲しみと絶望、言葉では言い表せない苦しみのせいで自分以外に目を向けられなくなる日々だ。
デニスの苦しみは、私が気がついていたより大きかったか、あるいは私はそれにまったく気がついていなかったのかもしれない。それは今後もわからないだろう。事実は、自殺に向けて努力したのに私は生き残り、デニスは亡くなったということだ。デニスが生きた人生を尊ぶ方法があるとすれば、私が知っている唯一のやり方は、自分の命を大事にすることだ。そのために今、できるだけのことをしている。
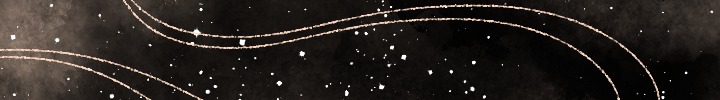
この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳:矢倉美登里/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan

