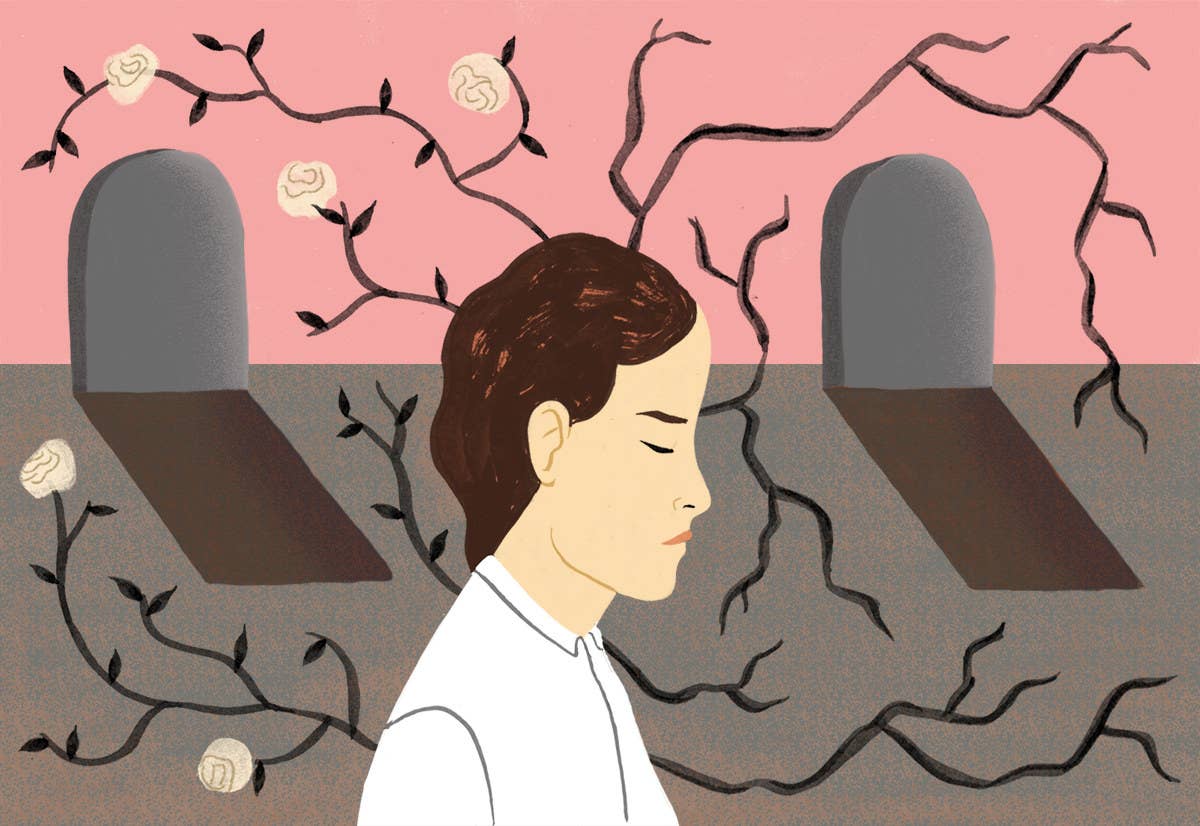
救急隊員が空の担架を救急車に戻すのを見た瞬間、ふたりとも死んでしまったのだ、とわかりました。家の斜向かいの野原の端で、私と私のふたりの兄弟を乗せた車の運転席に若い男の人が素早く乗り込んできました。「見つからなかったよ」彼は助手席の女の人に言いました。女の人は私たちの方を見て作り笑いを浮かべながら「お嬢ちゃん、あなたの靴はどこにあるって言ってたかしら?」と聞きました。「玄関の中」私は救急車のテールランプが、止まれの標識で点滅するのを見ながら答えました。女の人は車から出ていき、数分後に白いスニーカーを手に戻ってきました。「言う通りのところにあったわ!」彼女はそれを私に渡してそう言いながら、相方の男性に向かってはかすかに首を振りました。まるで「まいったわね…この子たちどうする?」とでも言うように。
やがて児童福祉職員はふたりとも前を向き、車が走り出します。私たちはアメリカ国道1号線を南へ向かいました。途中マクドナルドのドライブスルーに立ち寄りましたが、私は何も食べたくないと言いました。その後私たちは、どこか消しゴムと幼稚園の匂いのする政府系の建物へと案内されました。私たちは長い会議用テーブルに座り、兄と弟は発泡スチロールのトレーに入ったパンケーキとソーセージ、私には紙コップの水が与えられました。別の女の人が来てテーブルに座りましたが、彼女にはこの種の知らせを告げることに慣れた人特有の、ストイックな覚悟が感じられました。彼女は、私がもう百万年前に知っていたことを告げました。「僕たちはみなし子だ」弟があっさり言い放ちます。「違うわ!」ケースワーカーはあわてて否定します。弟は間違っていないのに。「私たちは何とかしようとしているの」別のケースワーカーが立ち上がって、ビデオデッキに『ターザン』を滑り込ませます。ここで孤児の映画? と、皮肉さを指摘して面白がることもできたかもしれませんが、私はそうはしませんでした。私たちは黙っていました。
私が多分4杯目くらいの水を飲んでいると、捜査員から別の建物に呼び出されました。氷みたいなエアコンの空気に震えながら、私は女性捜査員の前に座りました。茶色の髪に、優しそうな目。彼女は質問を次々に繰り出してきて、私はそれになるべくきちんと答えました。両親は結婚していましたか? はい、お母さんはいつも指輪をしていました。今朝もしていました。結婚式の写真があるかどうか、お母さんに聞いたことがあります。お母さんは、結婚するのに盛大な結婚式は必要ないのよ、裁判所で書類にサインすればいいの、と言っていました。どうして名字が他のみんなと違うのか聞いたとき、お母さんは、女の人は結婚しても名前を変える必要はないのよ、と言いました。お父さんはお酒をたくさん飲んでいましたか? 今朝は飲んでいましたか? いいえ、少なくとも私が知っている限りではそんなことありません。お父さんが何か飲むとしても、仕事の後にバドワイザーを1本か2本くらいしか見たことがありません。家にはお酒が常備されていませんでした。お父さんがこんなことをする兆候は何かありましたか? 私は話すのを止めて、これまでの奇妙な3カ月間を心の中で再生してみます。この質問が意味するほど大きな出来事は思い出せません。「わかりません」私は降参して認めます。
私の両親が無理心中したというニュースは、私たちが住んでいた小さな島のコミュニティに衝撃を与えました。私の母は地元の小学校のヘッドスタート(訳注:米国の低所得家庭の子どもに対する教育プログラム)のコーディネーターでした。父はコンクリートポンプの事業のオーナーとして成功していました。両親がコミュニティの中でよく知られていた分、コミュニティの反応も大きくなりました。私たち兄弟は一時的に、家族ぐるみの友人の家に引っ越しました。私たちは急な両親の死によって発生した、あわただしい遺産相続、葬儀の手配、家を売るための準備といったさまざまな雑用からは守られていました。私たちにとって、その後の日々は心理カウンセラーとの面接と、親しい人が届けてくれるカップケーキやオーブン料理などなどが混ざりあったものでした。イルカと一緒に泳ぐ体験を寄付してもらったりもしました。私はたくさんの哀悼する人たちに対し、ただ「ありがとう」と言うことを学びました。反射的に言いがちな「大丈夫よ」は、突如としてまったく不正確な言葉になっていました。
学校の図書館では、書物や学習を大事にしていた母にふさわしい、美しい追悼会が開かれました。会場はあっという間に埋まって、満席になりました。参列した人たちは、母にまつわるさまざまなエピソードを語ってくれました。母が受け持っていたヘッドスタートの子どもたちをふたり孫に持つおばあさんは、母が税金書類の提出を手伝ったときのことを話していました。ある移民の子の父親は、母がややこしい医療保険の手続きを教えてくれたおかげで、彼の息子が必要としていた心臓手術が受けられたのだと言っていました。私は今でも、そんな母の優しさに打たれています。
父があんな恐ろしい犯罪を犯していなくて、もし葬儀をしていたら、その場でどんなことが語られたのか、想像するのは難しいです。結局父の葬儀はしませんでした。そんな機会は、父がしたようなことをした人にさしのべられるものではないのです。父が亡くなった数日後、父側の親戚が私たち兄弟をスーパーに連れて行ってくれて、バラの花を買いました。私たちは橋のアーチのてっぺんに立って、花を入り江へと投げ入れました。そして「お母さんとお父さんは、世界一のお母さんとお父さんだったよ」と言いました。それだけでした。
数カ月後、母側のおじ夫婦と同居することになった南部の片田舎の小さな家で、私はベッドに座って、元の家から送られてきた箱を空けていました。自分で梱包しなかったので、中身は何でもないつまらないものから、事件前の生活での宝物までありました。ある箱に、母の追悼会のゲストブックと新聞の死亡記事の切り抜きの中に混ざって、コミュニティ紙「The Reporter」のセクションがありました。母と私はReporterを愛読していて、毎週新しい版が出ると、読者の手紙コーナーにコミュニティの知り合いが出ていないかと探したものでした。当時自分の意見を広く発信するには、Reporterに手紙を書くことになっていたのです。それは少なくとも、今ほとんど何も考えずにシェアされているツイートやステータスアップデートより、洗練されている必要がありました。当時はソーシャルメディアの始まりのほんの数年前ですが、完全に時代が違っていました。
とにかく、そこにはReporterの4ページ目があり、それはタイムカプセルに入れる宝物のように大事に切り取られていました。その記事には私の家族のこと、というかその消滅のことが書かれていました。それは2003年3月19日の朝に起きた出来事のありのままの記録でした。ディテールのいくつかはどぎつく、個人的なことに立ち入っていて、どうして記者がこんなことを知っているのかと不思議に思ったほどでした。その後になって、緊急電話の内容は公的記録なのだと知りました。私は気分が悪く、プライバシーを侵害されたような気持ちになりました。ページの隅には私の家の白黒写真があり、その周りには黄色いテープが張られています。写真は画質が荒く、細かいところがぼやけています。カメラの角度のせいで、玄関にきちんとかけられた「神がこの家を守りますように」のリースが見えません。ブランコの上のガンボリンボの木は見えますが、その下にあるはずのコンクリートのハートが見えません。
それは私たちがネコのイカボドを埋めたところでした。イカボド、別名イッキーは老猫で、その死は世界の自然な秩序の一部でした。私たちは彼が死んだとき、彼と一緒にいました。イッキーはキッチンの床の上の柔らかいタオルを数枚重ねたベッドの上に寝ていました。ガラスの引き戸を通して、太陽の光の筋がイッキーの上にかかっていました。母は彼の最期のときずっと、イッキーを優しくなでていました。その後私たちは、まだ温かいその体を最後にと何回かずつなでました。私は彼の毛を何房か切り取り、ジップロックに入れました。イッキーの柔らかさを忘れたくなかったのです。私たちが住んでいた島の土はサンゴの岩でできていてとても硬かったのですが、次の日父ができる限り大きな穴を掘りました。私たちは学校で古代エジプトの単元を終わらせているところだったので、イッキーのお墓には、死後の生に持っていくおもちゃやキャットフードを入れてあげたいと思いました。家族みんながガンボリンボの木の下に集まり、父と母がイッキーの話をしました。次に父が穴を埋めて、その上からコンクリートをかけました。穴は丸くなるはずでしたが、ハートの形になっていました。私たちはコンクリートが柔らかいうちに手形を付けて、一番上に貝殻を載せました。イッキーは島の猫だったからです。これは新聞には載っていない話です。
イッキーの死は私にとって、病院にいてほとんど会わないまま亡くなった祖母を除いては、初めての死でした。祖母の死は美化され、演出されていました。ICUの消毒薬の匂い。お通夜での、冷たく粉っぽい頬へのキス。厳粛に見えるように、お墓の写真では笑ってはいけないと知ったこと。イッキーの死はもっとリアルでした。私は彼が死んだことで、死とは終わってしまった生の再認識を伴うものだと知りました。それは人を結束させ、ロジカルな過程を経ていきます。でも両親の死は、このようなルールに従いませんでした。それは予想外で、混沌として、恐ろしいものでした。それは私の人生全てを爆発のように引き裂き、その跡にはほこりっぽい、煙たい粒子を残していきました。その直後はむせたり、つばを吐いたり、きれいな空気を求めてあえいだりして、最終的には時間とともに呼吸はしやすくなります。傷つかずに逃げられたと思うものの、吸い込んでいた毒はあらゆるすき間に残っていき、10年ほど温めておくとガンになってしまうかもしれません。それは本人が気づかないうちに、人を生きたままむしばんでいくのです。
こうして去年、私はセラピーに行った方がよいのかもしれないと判断しました。問題の核心は、私が両親に起きたことを誰にも言えずにいたことです。結婚して3年になる夫にすら、言っていませんでした。私は「結婚相手に隠し事をすると関係が破たんする」といった記事を読みすぎていたので、最終的にセラピストを探すことにしたのです。私の沈黙の根は深いところにありました。最初の数カ月間、私はもっとオープンでした。クラスメートや先生が、どうして7年生の最後に別の州に引っ越してきたのか好奇心で聞いてくると、私は「両親が亡くなったから、おじとおばの家に同居するために来た」と言っていました。私は同情されたり機嫌をとられたりする必要はないことを伝えようと、この話をするときは相手にしっかり目を合わせて、淡々と話しました。廊下の真ん中で、他の生徒が周りを歩いて行く中、数学の先生にこのことを話しました。州のテストの後、退屈して座っているとき、新しい友だちにも話しました。私の努力の甲斐なく、彼らの顔にはショックが浮かんでいました。
ほどなく私は自分を疑い始めました。私は社会的マナーに反しているのではないか? 青いマスカラを付けて、気のない相手に手紙をたくさん送り付けるのと同じカテゴリに入るのではないか? わかりませんでした。はっきりしていたのは、学校の終わりのある日、体育館で座っていたあのときの感覚は二度と味わいたくないということでした。そのとき、クラスメートと私は体育館の壁に寄りかかって座り、他の生徒たちがバスケットボールをするのを見ていました。なぜ多くの人が出ていこうとするこの町に私が来たのかを、他の生徒たちと同じように、彼女は知りたがっていました。私は自分の定型的な回答を返しましたが、次に彼女は、私が答えを用意していない質問をしてきました。「何があったの?」私は初めて、礼儀正しくあるために質問を控えない人に出会ったのです。私は凍りつきました。私はとっさに、この名前すら完全に覚えていない女の子に本当のことを言ってはいけないと思い、交通事故の作り話をしました。それはよくできていて、彼女の好奇心を満たし、その後は違う話題に移ることができました。でも私はそのときの教訓を忘れず、自分の中に引きこもり始めました。私は、カジュアルな会話ではおじとおばを「両親」と呼ぶようになりました。そのほうがシンプルで、簡単でした。詮索されにくくなり、弱点が少なくなりました。私は母と父を、心の中の要塞にしまい込むことができました。それは私にとって、自分の不快感を軽減しようとする試みよりも一番大事なことでした。
なぜなら「お父さんはお母さんを殺して、自分も死にました」というのは、非常に重い発言だからです。その意味するところはとても残酷です。まるで母が父に屈従し、虐待されていたかのように聞こえるし、父が家族を恐怖支配していたようにも聞こえます。でもそれは、私の実体験とはまったく違うのです。母はあらゆる種類の人権を脅かされている人たちの強力な代弁者でした。母は母であることが大好きでした。ハロウィンコスチュームを手作りして賞をもらったり、ガールスカウトがクッキーを売る募金活動のまとめ役を毎年務めたりしていました。また私の中に、世界への好奇心や学習への愛情を育ててくれました。父は私を私にとって初めてのダンス、ガールスカウトの父娘向けイベントでエスコートしてくれました。ディズニーワールドやユニバーサル・スタジオのあらゆるスリリングな乗り物に連れて行ってくれたのも父だったし、補助輪なし自転車への挑戦を助けてくれたのも父でした。このすべてがあって、それでも……実際私自身がその経験をしてもわからないのに、どうして他の人が理解できるでしょうか?
私は他人から与えられうる批判に長い間苦しんできましたが、最近ようやく、私を沈黙させてきた自分自身のこだわりについて気づきがありました。私は何より、家族についての誇りを失うことを恐れていたのです。私たちが本当に素敵な家族だったのなら、こんなことが起こるはずがない、と思いたくなかったのです。 加害者の子どもであると同時に恐ろしい犯罪の犠牲者の子どもでもあることは、他に見られないほど奇妙で、苦しい立場です。私は今やっと、父が私から奪ったものすべてのありがたさを本当の意味で感じ始めたような気がします。当時13歳だった私は、母がハイスクールの卒業式で私のスピーチを聞かないであろうことも、大学の寮に見送ってくれないことも、学士号、修士号を受け取るために舞台を歩く姿を見守らないであろうことも、わかっていませんでした。母は私が結婚式でバージンロードを歩く前、ドレスやベールを整えることもありませんでした。母は私が将来持つであろう子どもたちを腕に抱くこともありません。母は教師になりたいという自分の夢を叶えることも、もうできません。彼女は自分の子どもたちだけでなく、彼女を愛するすべての人たちから引き裂かれてしまったのです。
母を殺したことは言い訳できない犯罪で、多くの人が許せないと言うでしょう。私は父に対して非常に腹を立てていますが、それでも父の死を深く悲しんでいます。社会はこの種の悲しみを快く受け止めてくれず、私はそれをさまざまな小さな機会に、特にそのような考え方がソーシャルメディアで増幅されたときに、思い知らされてきました。たとえばコネチカット州ニュータウンの小学校でアダム・ランザが銃を乱射した事件で、彼はその直前に自分の母親も射殺していたのに、それが死者数に加わっていないとき。テロリストの遺体を処理した葬儀場に対して、ネット民たちが反対運動を起こしたとき。それはまったく理解できる反応です。一般に死者を悪く言ってはいけないと思われていますが、犯罪者はそう思われる権利を剥奪されるのです。社会的な動物である人間がそのような人物に与えうる最大の報復は、社会からの追放、そして抹消です。彼らを歴史から消し去ることで、私たちはコントロールを取り返すことができるのです。でもこのように悪者扱いされる人物の遺族には、喪失感が残ります。それは、亡くなった人が良い人物だったという確信の喪失感です。また自分は人間性を正しく判断できるという自信の喪失感であり、こうあってほしいと思った人たちに対する喪失感でもあります。それはいつまでも残る深い悲しみで、なかなか解消されません。その感情は多分、他の人と分かち合えないものだからです。私は半生を通じて、ただひとり自分の感情とともにあり、両親に本当に何があったのかを誰にも話さずに来てしまいました。
1月。私はクリスマス休暇が終わるまで待ちたいと思っていたのです。私が教会の広い駐車場に入っていくと、夫の白い車が見えました。そこは私のセラピストの駐車場でもありました。「迷わなかった?」私はわかりきったことを彼に聞きます。フリースジャケットのポケットに手をつっこんで、震えていることを夫に気づかれないように努めます。「これが終わったらヒバチ(訳注:日本の鉄板焼き)に行こうか?」彼はいつものように、あわてることなく落ち着いた調子で聞いてきます。「良いわね」私は答えますが、頭の中では「この後もあなたが、私と何か一緒にしたいと思うならね」と条件を付けているのです。セラピストが出てきて、私たちを迎え入れます。私はトイレに行って何度か深呼吸し、気持ちを落ち着けようとしました。この日のためにセラピストと一緒に準備してきたのだから、と自分に言い聞かせます。私はセラピストに、自分ひとりでこの話をする勇気を持てるかどうか不安だと打ち明けて、だからこの場で夫に話すことにしたのです。それでもセッションのための部屋に戻るとき、私のこめかみでは鼓動が激しく打っていました。加害者の子どもであると同時に恐ろしい犯罪の犠牲者の子どもでもあることは、他に見られないほど奇妙で、苦しい立場です。
セラピストは、セラピードッグが習得した技を見せているところでした。ルルはくるくる回ったり、お腹を見せたり、お座りしたりします。まずセラピストが最初に二言、三言歓迎の言葉を言い、その後は私が話す番になりました。私は半ばリハーサルしてきたせりふを始めます。「で、知っての通り、私の両親は私が小さいときに亡くなったけど、そのことをちゃんと話してこなかったでしょ。私は何年も、普通のハッピーな生活をしてきたの」私は強調します。「でもあるとき、父の様子がおかしくなったの。すごく疑い深くなって。新聞に、自分宛てのメッセージが載っていると思い込んでいたこともあった。そして何も証拠がないのに、母が不倫しているという考えに執着していった。どうすればよかったのか、誰にもわからなかった。それである日、父は母を殺して、自分も自殺したの」。私がこの8年間のほとんどにおいて悩んできた言葉は、5分もかからずに終わってしまいました。夫の顔を見ると、彼は親身な表情でうなづいています。「このことに気づいていましたか?」セラピストが彼に聞きます。「はい、なんというか断片をつなげて、そうだろうと思っていました」と彼は答えます。私はそれを聞いても驚きませんでした。長い間お芝居を続けるのは難しく、親戚の話の流れで口を滑らせてしまったこともあったからです。「こんなに長い間秘密を抱えてきたのは、とてもつらかったと思います」とセラピストが言い、「はい」と彼も同意します。彼は、場の重さのせいで私が落ち着かないことを感じたのか、私の腕を優しくさすって小さな声で「Let it go、Let it go」と歌い出します(訳注:「Let it go」は映画『アナと雪の女王』の主題歌、「そのままにしておこう」「あきらめよう」の意)。私をあやすにはディズニーが一番だと知っているのです。緊張が解けて、みんなで笑いました。その後私たちはヒバチを食べに行き、私は自分がまるで空気になったように軽く感じました。骨の重さを感じませんでした。
あの家の階段を降りてまったく違う人生を踏み出してから、13年が経ちました。苦しみの硬い刃が忍び込んできたように感じるとき、私は感謝の気持ちで立ち向かうことにしています。あのとき、おじは立ち上がって自分を犠牲とし、私たち兄弟3人を育て、一緒に成長させてくれました。祖母はよく私の母代わりになってくれて、人生のアドバイスから、病気のときに様子を見に来ることまで、いつでも頼りにしています。素晴らしい夫がいて、その両親も私の味方になってくれています。
それでも私の住んでいた町に行くといつも、私は子供の頃の家の前を車で走ります。その場所はもう変わってしまいました。私たちの家の広い裏庭となっていたふたつの区画は売られ、家が建っています。それぞれの家はお互いに軒近で、居心地悪そうに見えます。自生していた木は切り倒されていました。家の主たちは芝生を生やすのをあきらめて、芝生があった部分には砂利が敷き詰められています。白い家に白い前庭という風景は荒涼としていて、歓迎されている感じがしません。それは、かつての姿ではありません。そして私も、かつての自分とは違うのです。
この記事の著者は家族のプライバシーを尊重するため、匿名を希望しています。
この記事は英語から編集・翻訳されました。
