「救急搬送は断らない」という方針を掲げ、年間約1万台の救急車を受け入れる、愛知県豊明市の藤田医科大学病院ER(救急外来)。一般的には重症患者にのみ対応する大学病院のERとしては異例で、「藤田市民病院」と揶揄されることも――そんな同院ERに密着取材を実施。記者の目に映った現場の様子を紹介します。
研修医の受難
適切な指導であるとわかっていても、注意されている人を見るのはなんとなく、胃が痛いものだ。
きっかけは一人の研修医が「バイタル正常です」と上級医に伝えたことだった。すかさず「えっ、正常? 血圧93/53でしょ?」と聞き返す上級医。
「あんなぁ、基本、高血圧の高齢者が、低血圧やったらそれだけでやばいやろ。これじゃキミの言うこといちいち疑わなアカンようになるで」
こうして始まった、ある日の当直。スタッフは日中の半分、うち医師は上級医2〜3人と研修医3〜5人が勤務している。
0時になる少し前、夜勤ERリーダー医師の瀬川さんが「CPA(心肺停止)来るよー」と呼びかける。
70代前半の女性患者、Fさんは、入浴中に同居する家族によって発見された。
夜、家族は帰宅時にFさんが風呂場にいると気づいたが、そのときは異常だと感じなかった。1時間後に「さすがに長すぎる」と不審に思って踏み込み、Fさんが発見された。救急隊の到着時点で、CPAの状態だったという。
生活を共にする相手でも、異常に気づけないことはある。2017年中の救急車による搬送者の内訳のデータによれば、搬送時点で重症の患者が8.4%、死亡の患者が1.4%いる。
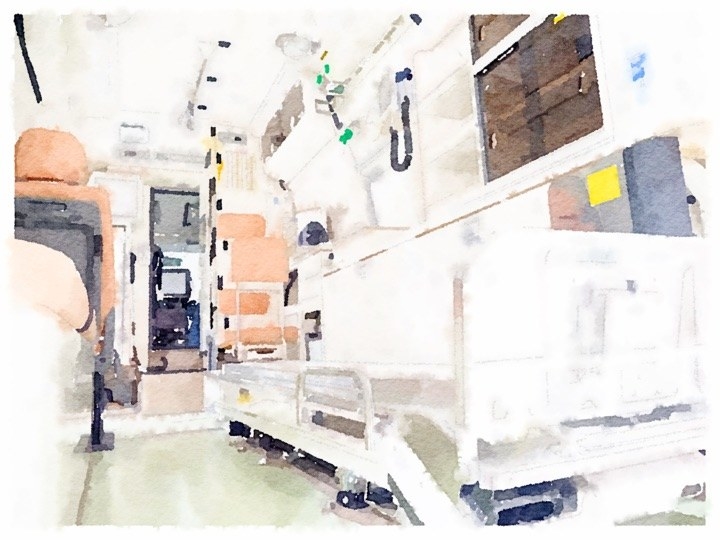
発見時のまま搬送されたFさんは、全身から血の気が引いた、青白い肌をしていた。口にだけ、たらりと一筋、真っ赤な血が垂れている。
夜勤帯でスタッフが少ないこともあり、自動胸骨圧迫(心臓マッサージ)装置を使用していた。
自動胸骨圧迫装置は人間による胸骨圧迫と同等の効果が得られることが研究結果で示されており、同院ERでも導入されている、とのことだっだ。
患者の胸部をアーチ状に覆い、中央のポンプが自動でシュコシュコと胸骨圧迫を続ける。その間、スタッフは手が空くため、並行して他の処置ができる。
突然、プシャッという音がした。
Fさんの口の中に溜まっていた血が、頭部付近にいた前述の研修医の白衣にかかった。量が多く、腰から下が染まる。「あー」と漏らすも、すぐに白衣を脱いでスクラブ(半袖Vネックの医療用作業着)姿になり、そのまま処置を続行する。
意志を失った体が装置によって、小刻みに揺れ続ける。瀬川さんが「ご家族に説明してくるわ」とその場を離れた。
家族の意向もあり、心肺蘇生は終了した。瀬川さんが「今日は亡くなる人が多いな」と小声でつぶやく。
Fさんの御遺体はCT撮影をすることになった。なぜ、死後にCTを撮影するのか。それは「原因検索のため」(瀬川さん)だという。
「今回のケースでは、状況だけでは死因が“水没死”、つまり外因死になってしまう。病気など、他に原因がなかったのかを調べなきゃいけないんですよ」
研修医に対して、見下した態度を取る患者もいる。取材中、ある患者は研修医に向かって「ちゃんとした医者を出せぇ!」「何かあったらどうするんじゃ!」「研修医はもうええ、下がれ!」と大きな声を出した。
研修医は上級医とアイコンタクトをして、スッとその場を離れる。
「ERにはね〜、研修医が多いんですよ〜。研修医がいないと成り立たなくてね〜」と優しく患者に伝える上級医。
少し時間が経って、患者がボソッと「ようわからんやつらに囲まれるの、イヤなんや……」と言うのが聞こえた。
まどろむER
瀬川さんが「救急車がずっと鳴っててぜんぜん寝れんわ」とぼやいたのは、時計が午前1時を回った頃だ。日をまたいで以降も、断続的に消防からの電話がかかり続けている。
当直の医師らは0時以降、日勤医師が出勤する朝8時までの時間を、2〜3人ずつのグループに分かれて交代で寝る。
すでに4時から担当する医師の姿はERになく、瀬川さんと研修医たちで治療に当たっていた。研修医は主にウォークイン、つまり時間外に歩いて来院した患者の診察をする。
その待合室に、明らかに雰囲気の違う男性5人組が現れたのは、2時少し前のことだった。地味な紺色のジャンパーにスラックスという出で立ちで、荷物が多く、目つきが鋭い。警察官だった。
風呂場で発見されたFさんは警察としては不審死の扱いになるため、検死が必要。「搬送は何時ですか?」「死亡確認は何時ですか?」など、取り調べのような質問が矢継ぎ早に投げかけられる。
スタッフにも疲れが見える中、深夜のERにピリピリした空気が流れる。警察はCT画像を証拠として確認し、パソコンのモニターごと写真を撮影して、帰っていった。
3時になる前、救急搬送は少なくなった。カルテ記入中に船を漕ぐ医師もいる。しかし、電話が鳴るとパッと覚醒。それが院内各部署からの連絡で、看護師が対応しているのを確認すると、再び船を漕ぐ。
そんな繰り返しで時間が過ぎていく。
ERの外、患者や付き添い用の待合ソファには、この時間でも5〜6人の姿があった。白い蛍光灯の光で、時間とは不釣り合いに明るい。多くは付き添いだが、点滴を打たれながら寝ている患者もいる。
待合室に置かれたテレビでは、深夜アニメが流れている。目を向ける人はいない。夜勤の事務員はひどく疲れた顔で宙を見ていた。賑やかなアニメのセリフだけが部屋に響いている。

記者は院内を少し、歩いてみた。非常用の電灯しか灯らず、暗い廊下には、この時間でもポツポツと人影がある。遅くまで働き、ようやく帰宅する他科の医師や看護師たちだ。
4時前、完全に動きが止まった。デスクに突っ伏していた医師が顔を上げ、「あれ、もうすぐ(交代の)4時じゃん」とあくび混じりに独りごとを言う。
後半チームの医師が起きてくる。「CPAまた来たんだよ」「マジすか? どこすか」「いや……、もう終わった」そんな会話をしながら、コンビニなどでよく見かける、フェイシャルシートで顔をゴシゴシと拭く。
眠いのか、しばらくはボーッと、この間に搬送された患者のカルテを眺めていた。
厚生労働行政推進調査事業費『病院勤務医の勤務実態に関する研究』のタイムスタディ調査では、救急科医師の仮眠時間の平均は4時間38分だった。
しかし、この調査では、医師が連続した仮眠時間を確保できていない場合もあると指摘されている。
その例として挙げられている、6時間の仮眠時間を確保できている外科医師の最長連続仮眠時間は1時間45分。救急外来での診療を含め、仮眠中に起きたのは5回以上。細切れの睡眠であることがわかる。
夜の病院で働くスタッフは医師や看護師、事務員だけではない。ある患者に膝のレントゲン写真が必要になり、ポータブルのレントゲン撮影機器が到着した。自分の体よりも大きな機器を運び込んだ女性の放射線技師が、そのまま撮影する。
まどろんだERの中で、その技師だけがテキパキと動き回っていた。
命を選別「怖い」
5時を過ぎ、にわかにERが忙しくなる。
まず2台、続いて3台の救急車。明け方は心臓病の「魔の時間」と言われるように、循環器の患者が多い。
夜勤帯、後半のリーダー医師は後期研修医の近藤さん(仮名)。ちょっと前まであくびばかりしていたが、切り替えは早い。消防からの電話を受けた直後から、テキパキと準備を始める。目が覚めているというよりは、体が覚えている、といった様子だ。
うち一人、60代前半の男性患者、Gさんは「胸の痛み」で搬送された。顔面蒼白で、顔には大量の冷や汗がしたたっている。呼吸数も多く、時折、ストレッチャーの上で苦しそうに何度も身をよじる。
Gさんは重度の心肥大を指摘されていたが、病院に行かず、自己判断で断薬。たばこ、飲酒も継続していた。
「心臓が悪いって言われてたみたいだけど、薬は飲んでなかったですかね?」そう聞かれ、苦しそうにうなずく患者。「たばこは?」「お酒は?」「寝る前にどっちもやった?」すべてにGさんはうなずいた。
「なるほどね」「今、楽になる薬を使いますからね」どんな理由であれ、近藤さんは患者を責めることをしない。

ERを取材していて度々、出会うのは、自己判断による断薬や、飲酒や喫煙などの生活習慣により、病気を悪化させてしまう人たちだ。
世間では医療について自己責任を持ち込む議論も根強く見受けられる。医師としてはどう感じるのだろうか。
同院ERを束ねる救急総合内科教授の岩田充永さんは「“この人に医療を提供する意味がない”というのは、現場が思ってはいけない」と強調した。
「どんな人にどこまで医療を提供するのか、という議論は社会としては必要でしょうが、現場の医師が命の選別をするようになるのは怖いことです。どんな患者さんであっても、少なくとも苦しいのは取る必要があるし、ERに来た以上は、やっぱり助かりたいはず」
一方で、「“(医学的に助かる見込みのほとんどない場合)このCPAが搬送されて何ができるのか?”とは、みんな心の底では思ったことがあると思う」とも述べる。
その上で、「感情を押し殺して沈黙していると燃え尽きてしまうから、そういう抱えたモヤモヤを誰かと話す機会がある方が健全だとも思います」とした。
Gさんの処置が終わったタイミングで、近藤さんと少し話した。患者の死には慣れるものか、質問すると少し黙った。
「……やっぱり、慣れはします。でも、慣れない部分もあるかな」
「三次救急病院ですから、かなり状態の悪い人が来るので、死はたしかに身近です。でも、医学的にみて助かる見込みが少しでもあれば助けたいし、万が一、見込みがとても薄いとしても、家族とか、患者さんの周りの人のことも考えてしまう。助けたいですよね。その意味ではまだまだ慣れないです」
答えのない問い
朝、7時半頃から日勤の医師たちが続々と出勤しだす。そんな中、小さな騒動が起きた。看護師が「先生たち、初療室3の患者さんに何分、接触した?」と聞いて回っている。
「マジかー」「さすがにわかんないよ」事情を聞いたスタッフが、口々にぼやく。
80代後半の男性患者、Hさんのことだ。転倒して搬送されたが、認知症があり、どこを痛がっているのか、尋ねてもよくわからない。CTを撮影すると、腹部大動脈瘤と腰の骨折があることが明らかになった。
子どもと二人暮らしだが、子どもは父親について「勝手に生きている」「知らない」とスタッフに言い放ったという。
「あのご家族はちょっと……難しいね」経緯を知るスタッフは首を横に振る。Hさんは日々の介護や医療を受けられない、ネグレクトが強く疑われる状態にあった。
そんなHさんに、結核感染の可能性が判明したのだ。
以降、全員がより感染防御力の高いマスクを装着し、治療に当たることになった。

近藤さんが「落とし所がわからない感じですね」とポツリ、漏らした。「落とし所」とはつまり、患者の行き先をどこにするのか、どこまでを治療のゴールとするか、だ。
循環器疾患、骨折、感染の疑いのあるHさんは、引き受け手を決めるのが難しい患者。医療の高度専門化の弊害で、複数領域にまたがる患者はどの科でも敬遠されがちだ。Hさんは結局、救急総合内科での入院となった。
状態が改善して退院できたとしても、入院前の環境に戻るだけなら子どもによるネグレクトが続く可能性もある。しかし、こうしたことは「ERで医者をしていると、よくあること」(近藤さん)。
多くの人が職場に向かっているであろう、人によってはまだベッドの中にいるかもしれない、ある朝。
ERの医師はこうして、睡眠不足の頭で、答えのない問題を考え続けている。
多くの勤務医が過労死ラインの前後で働く現状を背景に、医師の働き方改革の議論が盛り上がっています。一方で、医療の現場で実際に何が起きているのかは、世間にはあまり知られていません。
医療者たちはただ過重労働にあえいでいるのではなく、日々、プロフェッショナルとして患者の命を救いながら、生命倫理と社会的要請との間で葛藤し、自身も一人の人間として、理想の働き方を追い求めていました。
どんな議論も、その実際の様子を知ることで始まります。そこで、BuzzFeed Japan Medicalでは、記者の朽木誠一郎( @amanojerk )が藤田医科大学病院ERに一週間の密着取材を実施。医療現場の様子を紹介します。

