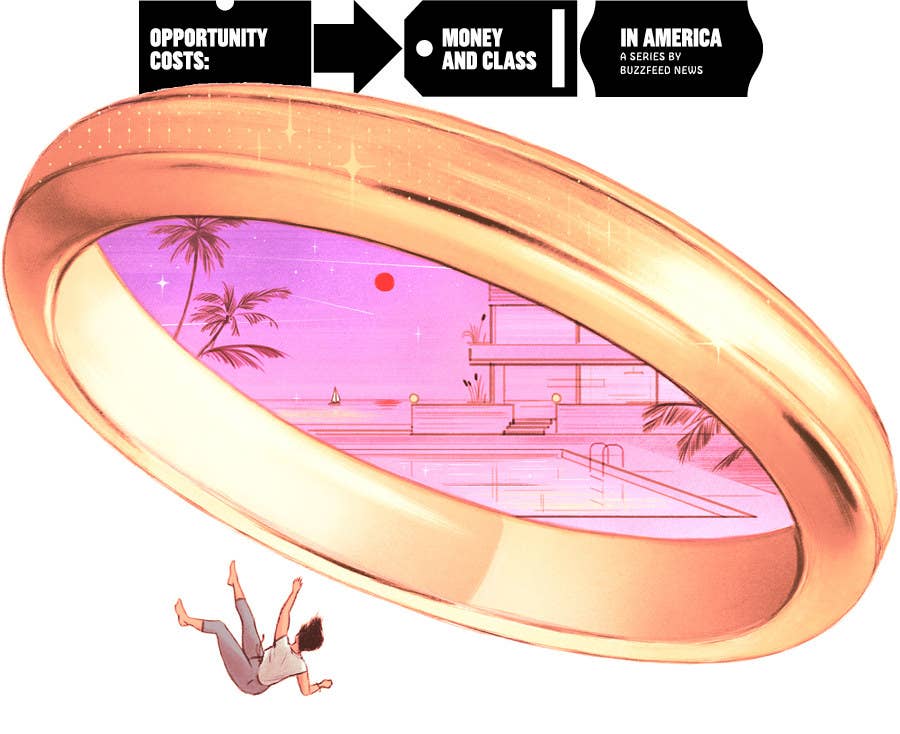
BuzzFeed Newsは、米ラジオ局WNYCのポッドキャスト番組『Death,
Sex & Money(死とセックスとお金)』と協力し、階級や金について、そしてそれらがわれわれの人生や人間関係に与える影響について取り上げたシリーズ『Opportunity
Costs』(機会のコスト)を公開している。以下は、著作家ジェイミー・シートンのエッセイだが、こちらでは彼女のインタビューも聞くことができる。
2008年、バラク・オバマ氏の最初の大統領選挙戦のときのこと。2人の子どもを連れて、ワシントンDCの友人のもとを訪ねていた私は、オバマ陣営の高位の人物からメールを受け取った。オバマ候補が参加するレセプションに招待されたのだ。レセプション前日、夫と電話で話していたときに、「そう言えば」と招待されたことを話し、行くつもりはないことを伝えた。
「どうして行かないの?」と夫は驚いた。
「だって2300ドルもするのよ!」と私は答えた。
「小切手を書けばいいだろう」と夫が答えた。
次の日の夜、私は、未来の大統領と何とかして握手しようとする支援者たちの最前列に立っていた。私の番がきたとき、自分はバンコクで暮らしているが、オバマ氏のための資金集めのイベントを開催して1万ドル集めたことを伝えた。
「ありがとう――バンコクは昔から縁があるのです」。オバマ氏は笑顔でそう言い、次の人に移った。オバマ氏と話したのは5秒ほど。1秒当たり約500ドルだった。
このころは目くるめく日々を過ごしており、数千ドルの小切手を切ることは、私にとって珍しいことではなかった。夫はタイのシティバンク銀行CFO(最高財務責任者)で、私は『ニューズウィーク』誌の通信員だった。ゲートのある高級住宅地で、プールつきの3階建ての家に住み、子どもたちは私立のインターナショナルスクールに通わせた。先生方も素晴らしかったが、プールが3つと無数のテニスコートがある学校だった。家のことは、女性のお手伝いさん2人が手伝ってくれた(お手伝いさんは、私が仕事をしているときに、掃除や料理をし、子どもたちの面倒を見てくれた)。親切な男性運転手もいた。年齢はそれほど変わらなかったが、父親のような優しさで私を見守ってくれた。
バンコクでの2年間のあとは、シンガポールで2年間過ごした。夫はシティバンクの上級役員で、私はフリーランスのジャーナリストとしてだ。シンガポールでも、同じように贅沢な家に住んだ。7年前に南アフリカで結婚した私たちが、本当にお金を手にしたのはこのころが初めてだった。そして私たちは、それを存分に楽しんだ。街で一番おしゃれな地域の、最も豪奢なアパートメントに家を借りた。白い大理石の床と、プライベートのエレベーターがついた、ベッドルーム4部屋のアパートメントだった。
このころのことは、はるか遠い昔のように思える。2011年、私たちはアメリカに戻ることにした。1つには子どもたちが、狭い外国人コミュニティで特権を与えられて育つことに不安があったからだ。子どもたちには、もっと「普通の」アメリカの子どもとして暮らしてほしかった。そして1年後、夫は浮気相手の妊娠を理由に去っていった。
元夫は現在、新しい家族とマンハッタンに住んでいる。子どもたちと私は、ニューハンプシャー州の私の故郷の町の中心部にある、スプリットレベル(階が段違いになった)の家に住んでいる。子どもたちは、私の母校である安全で優秀な公立高校に通っている。相対的に言えば、私たちはとても運がいい。しかし、個人トレーナーつきのジムや、スパの予約、パーティーの計画、母親として協力する学校行事などで埋め尽くされたかつての日々は、今や、生活のために仕事に追われる日々に取って代わった。元夫からの扶養料で賄いきれない分を、フリーランスのジャーナリストとして売り込みをし、記事を書いて埋めている。原稿料が入るまで買い物に行けない週もある。
仲の良い友人たちには、自分の新しい現実を包み隠さず話しており、彼らは親身になってくれる。でも今の私は、彼らとは違う世界に住んでいると感じ、そのことを意識してしまう。100万ドルの豪邸にお邪魔して、別邸を賃貸に出す話を聞きながら、「去年うちの子どもたちは、朝に目が覚めたとき暖房がなかったのよね。暖房用のオイルをタンクに入れるお金がなかったから」などと考えているのは辛いものだ。
新しい自分になって5年。52歳でお金の心配をしなければならないことに、今も憤りと苦痛を感じる。こんなはずではなかった。ときどき、真夜中に冷や汗をかいて目が覚める。明るいどころか、安定さえも程遠く見える未来を思い、パニックになるのだ。ここ1年は、私の個人的な状況に対する不安と、アメリカの未来に対する強い恐れや不安とを、並行して感じていた。国レベルの脅威を感じるたびに、私自身の状況は大したことではないという思いが強くなった。私より大変な人はたくさんいる。自分が恵まれていることはよくわかっている。それでも、子どもたちと自分が失ったものを嘆かずにはいられない。
お金のない状態に慣れるよりも、お金のある状態に慣れる方がずっと簡単だ。しかし実を言うと、私が今置かれている金銭的な状況は、私にはずっとなじみのあるものだ。私はずっとこうなるべきだったのだろう。モノポリーのゲームのようにお金を使った夫との日々は、バカげて自分勝手な甘い夢だったのだ。
幼いころから私は、経済状況が異なる2つの現実を生きていた。私がまだよちよち歩きのころに両親は離婚し、まだ若かった母は再婚したが、再婚相手は、決して定職につかない、自由な気ままな人だった。2人はいつも金銭的危機に陥っていて、私はそれを敏感に察していた。いっぽう、休暇になると実父と過ごした。父は私たちを、バハマへのエキゾチックな旅に連れて行ってくれた。バハマでは自家用飛行機に乗って、52フィートもある自家用クルーザーまで飛んでいった。私はこの2つの世界を行き来し、お金がなくてもお金持ちに見える方法を早いうちに学んだ。私は友だちが着ているような高価な服を買うため、6年生のときに、家を掃除するアルバイトを始めた。高校時代はずっと、10種類以上の臨時雇いの仕事をしていた。
ボストンでの大学時代は、すべての費用を自分で払っていた。一時はホームレスになったこともある。最終的には、マサチューセッツ工科大学(MIT)で外国人学生向けの寮に空きを見つけ、掃除をする代わりに住まわせてもらった。私は、多くの大学生がそうであるような、単なる貧乏ではなかった。貧しくはあったが、高校時代に買った高価な服をまだ持っていたし、父は裕福だったから、周りの人は私が貧乏だとは思っていなかったと思う。もっと大事なのはおそらく、私自身が自分のことを貧乏だと思っていなかったことだろう。私は自分が父の世界に属している気がしていた。そして、いずれそちらの世界に戻ると決心していたのだ。
大学を出ると、ワシントンDCに住んだ。大手法律事務所で働く年収数十万ドルの法律家の知り合いがたくさんいた。私自身は、新聞社でリサーチを手伝う仕事をし、夕飯には、中華のテイクアウトで1ドルのライスを持ち帰ることもたびたびだった。少しでも余分なお金があれば、仕事で定期的に参加していたフォーマルなディナーに着ていく服に消えた。上司が「海外で特派員として働ないか」と持ちかけてきたときは、躊躇しなかった。私は南アフリカを選んだ。マンデラ氏が大統領である間に住んでみたかったのだ。そして1996年、私はこれまでの生活をあとにし、ヨハネスブルグに移った。
元夫に出会ったのは、その数週間後だった。私は特派員として何とか生計を立てていた。質素な一軒家に住み、デートで連れて行ってもらうディナーで、まともな食事が食べられるのを楽しみにしていた(5大大手企業の1社で働く前途有望な会計士だった元夫は、私を頻繁に食事に連れて行ってくれたのだ)。おごってもらうことは気にならなかった。なりたかった特派員になれたのだから。それに、お金に苦労するのは慣れていた。私たちは3年後に結婚した。そのころには、彼は出世の階段を上り始め、私はライターとしてたくさん仕事をもらっていた。
2000年に娘が生まれたあと、元夫はニューヨークで仕事を得たため、家族でコネチカット州の裕福な町に移った。そこでは私は、ほぼすべての時間を、妻と母親業に専念した。娘との生活を通して、自分たちよりずっと裕福なたくさんの夫婦と知り合いになった。そこで出会った奥さんたちはみんな、夫がヘッジファンドで大成功していたり、実家が金持ちだったりで、かつてはキャリアを持っていたが今は家庭の主婦、という人たちだった。彼女たちは、面白くて率直で常識ある友人たちだったが、私は、自分たちの家が彼らの家より質素で、自分がデザイナーブランドの服を持っていないことが気になっていた。
私はまだフリーのジャーナリストをしていたけれど、ベビーシッターの代金は、私の稼ぎより高くついた。でも、ジャーナリストとして働かないという生活は想像できなかった。夫が稼いだのではないお金で、夫にプレゼントを買える自分でいたかった。でもそれよりも、お金が十分ではなかったときの記憶が染みついていた。金銭的なセーフティーネットが必要だったのだ。
夫がシンガポールでの仕事に採用されたとき、私たちは、まさに宝くじに当たったように感じた。それまでの生活は、確かに貧乏ではなかったが、いつも豊かとは言えず、2003年に息子が生まれてからは特にそうだったのだ。しかし、ベビーシッター代を節約するために日曜日に交替で映画に行く生活から、一転して、住み込みのお手伝いさんがいる生活に変わった。夫の仕事には、住居や自家用車、子どもの私立学校の授業料、好きな会員制クラブの会費、そして、アメリカからの輸入食品を買うための手当など、至れり尽くせりのサポートがついていた。すべて、給料とは別にだ。
生まれて初めて、私はお金の心配をする必要がなくなった。夫は、「働くのはやめて、ほかの外国人の奥さんみたいに、アメリカン・クラブのプールサイドでのんびり過ごしたらどうだい」とさえ言ってきた。でも、プールは好きだけれど、私にはまだ野心があったし、自分の手で稼ぎたかった。私は、地元の雑誌に定期的に記事を書く仕事を得た。それから、「ジャック・ロジャース(Jack Rogers)」の靴をアメリカから輸入するビジネスを立ち上げた。あのころ一番誇らしい瞬間は、靴がたくさん売れて、毎月の請求を私の稼ぎで払うことだった。そんなことは1回しかなかったが。
お金を持つ生活には、なんと早く慣れるのだろう。同じような人たちに囲まれていればなおさらだ。私たちは、世界中から来た人たちと広く交流を持った。彼らの共通点は「富」だ。すぐに私たちは、贅沢なパーティーに参加したり、パーティーを自分たちで開いたりするようになった。週末にフェリーでインドネシアに出かけ、学校の休みには飛行機でプーケット島に行った。その夏、アメリカに一時帰国したときは、お手伝いさんも一緒に連れていった。飛行機で東海岸の友だちを訪ねて回ったのだ。私は新しい自信を身に着けていた。ついに、コネチカットの友人たちと同じデザイナーブランドの服を手に入れた。そして、支払いに何の躊躇もしなかった。私は彼女たちといつも親しくしてきたし、彼女たちはずっと私の力になってくれた。しかしその夏は、初めて自分が彼女たちの仲間であると感じた。今ならわかる。私のその自信は、ほとんどがが、自分の経済的そして社会的立場に由来するものだったが、そのどちらも、夫からくるものだった。
ワシントンDCでオバマ氏と握手をしたころには、私は、自分たちの裕福な世界に慣れてしまっていた。そして多くの意味で、その世界に完全になじんでしまった。そのお金を夫が稼いでいるということは気にならなかった。私たちはチームだし、私は子どもたちを育てているのだから。しかし私はまだどこかで、ホームレスの大学生であり、トイレを掃除していた少女だった。どれだけ多くのものを手にしても、私は働く必要があった。そして心のどこか奥底では、私たちは、集まってくるこの富に値しないと感じていた。夫は、シティバンクの仕事に就く前は、「銀行家なんて、みんな刑務所に入るべきだ」と言っていた。しかし今や彼もその1人になった。私はひそかに、いつかすべてが崩れてしまうのではないかと恐れていた。
そしてもちろん、すべては崩れた。私は、たとえ地面が崩れたとしても、夫と私は一緒に立ち向かうのだとずっと思っていた。まさか経済的な保証の終わりと、家族の崩壊が同時に起こるとは、夢にも思っていなかったのだ。
2012年11月のある暖かい日に、夫がそのことを打ち明けたとき、私はたちまちサバイバルモードになった。夫が私たちの生活を粉々にしたことを理解しようとした。取り乱さないよう努めながら、子どもたちは必ず扶養されるようにしなければと考えていた。私はいつも、自分の結婚をパートナーシップだと考えてきたが、実際には、夫がすべてのカードを持ち、私は彼の力に完全に頼り切っていた。私たちは生活費のために共同の銀行口座を持っていて、そこに夫が毎月お金を入れていた。週末には現金も渡してくれた。彼が別の女性と関係を持ち、子どもをもうけることができるなら、私たちから去っていくこともまた可能なのだと私は悟った。
夫から浮気のことを聞いた数日後、ニューハンプシャー州の家の高いローンを夫が払い続けるのか、ましてや、毎月の請求や食費を払ってくれるのかわからないまま、私は自分の銀行口座を開設した。臨時のライター兼編集者の職に応募し、採用された。オフィスのトイレで泣いてばかりいたが、何とか仕事を遂行し、自力でいくばくかのお金を稼いだ。仕事のおかげで、自分をコントロールするという大いに必要な力が得られたが、当時12歳と9歳だった子どもたちには多大な犠牲を強いた。2人は、家で私を必要としていたので、この仕事が終了すると、次の仕事は探さなかった。その代わり、フルタイムのフリーランス・ライターに戻ったのだ。
一時的な援助金について弁護士を通して争っている間、夫は毎月の請求書に支払いを続けてくれたが、私は裁判所命令なしでは常に不安を抱えていた。でもおかしなことに、自分の現実から目を背けてもいた。私の弁護士は、「あなたのような女性」にとっていちばん難しいことのひとつは、今まで知っていた人生が終わったことを理解することだ、と言った。順調だったとき、自分はその世界の「典型的なタイプ」だと思っていた。そして突然、今度は別の世界の「典型的なタイプ」になった。若い女のせいで捨てられた中年の妻だ。初めのころは、父親のしたことのせいで、子どもたちが家を出なければならなかったり、あるいは経済的に困ったりすることがあってはならない、と頑なに思っていた。だから私たちは、以前とほぼ同じ生活を続けていた。田舎の5000平方フィートの家に住み、最初の春にはフロリダの家まで旅行した。
女友だちが言い張るように、自分はひどい目に遭った側なのだから、離婚に当たっては多額のお金をもらえるだろうと考えていた。しかし実際はそうならなかった。まず、ニューハンプシャー州の法律では、夫からもらえる扶養料は「リハビリ的」なものなので、数年間しかもらえない。それに加えて、元夫は解雇された。新しい仕事に就いたが、給料は下がった。そして、新たに生まれた子も養わなければならなかった。離婚が成立するまで4年近くかかった。その間に私は、元夫には反対されたけれど、もっと小さくて家賃がずっと安い家に引越をし、支出を抑えた。それでも、調停に従って、私は月に約2000ドルを稼がなければならず、毎月、自分に課せられた義務を果たせるだけの仕事を得るのに大変な思いをしている。扶養料は徐々に減っていき、そのうち終わるということが、常に頭のどこかにある。
繰り返しになるが、私は若いころ、経済的に異なる2つの世界に生きていた。そして今、その歴史は繰り返され、子どもたちもその世界を生きている。数年前の夏、仲の良い友人が、私たちをバハマの彼女の家に招待してくれた。もちろん、宿泊費はかからなかったが、それ以外はすべて払わなければならず、夏休みの間中、気が気でなかった。ある夜、みんなで夕食に出かけ、彼女へのお礼のつもりで夕食代を持とうと思った。限度額ぎりぎりのクレジットカードを出したときは、軽くパニックを起こしたのを覚えている。うろたえるあまり、口を開くことができなかった。次の夏も彼女は招待してくれたが、断わるしかなかった。
お金があったときは、まったく躊躇せず使っていた。お金はただそこにあり、永遠にあるものだと思っていた。今はお金のことで頭がいっぱいで、どんな少額の買い物でも、毎回よく吟味する。先日は、仲の良い友だちが出ている芝居を見逃してしまった。チケットを買うための20ドルを捻出できたときには、もう売り切れていたのだ。残念ながら、芝居を見に行けなかった理由を彼に話しても、信じてもらえないだろう。彼の世界では、誰もが20ドルくらいは余分に持っている。そして彼は、まだ私がその世界に属していると思っているのだ。
貴重な教訓を得た、と言えるようだったらいいと思う。「お金で幸せは買えない」とか、「以前より貧しくはあるが、正真正銘独立した人生を生きていることをありがたいと思っている」と。素敵な言葉だが、そう感じたことはない。私はお金がないことが嫌いだ。どうやって支払いをするかに頭を悩ませるのはストレスが溜まるし、ほかのことを考える余裕がほとんどなくなる。お金で幸せは買えないかもしれないが、安心と心の平穏は買える。そしてそれらが幸せを支えてくれるのだ。
シンガポールで過ごした最後の年、私は、子どもたちが贅沢な外国人コミュニティで成長することでダメになるのではないかと心配していた。そして、夫が去ったときは、子どもたちに十分な環境を与えられないのではないかと心配した。今もその心配はある。昔は子どものことに積極的に関わる母親だった。学校の活動には常に進んで参加し、パーティーや遠足を企画した。自分の時間と気持ちを子どもに集中させられるだけの贅沢があり、そうした生活を愛していた。しかし夫が去った直後は、それまでと同じように子どもたちの面倒を見るのは、精神的に無理だった。家庭料理の代わりに、長いこと、テイクアウトの総菜や冷凍ピザが並んだ。ありがたいことにそうした日々は終わったが、今は、生計を立てるために週7日働くこともたびたびある。
夫に戻ってほしいとは思わないが、昔の生活を取り戻したいと思うことはたびたびある。子どもたちがFacebookで、昔の友人家族が外国の5つ星ホテルでバカンスを楽しんでいる写真を見て、羨ましいと感じているのは知っている。贅沢を羨んでいるのではない。完全な家族であることを羨ましく思っているのだ。それを再び手に入れるためなら、私たち3人は、これまで使ったお金をすべてあげてもいい。
ジェイミー・シートンは、ニューイングランドに住む著作家、ジャーナリスト。『ニューズウィーク』、『ワシントン・ポスト』、『オー、ジ・オプラ・マガジン(O, The Oprah Magazine)』をはじめ数々の出版物に、ニュース記事やエッセイを書いている。
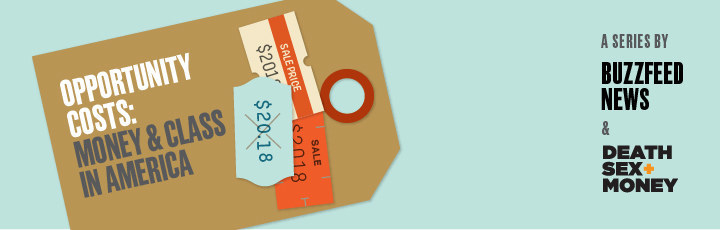
この記事は英語から翻訳されました。翻訳:浅野美抄子/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan
