国が長年にわたって実施してきた政策によって苦しんだのは、当事者だけではなく、家族も同じだった。
6月28日、熊本地裁で「ハンセン病家族訴訟」の判決が言い渡される。ハンセン病隔離政策によって苦しんできた、家族たちによる初めての集団訴訟だ。
原告は元患者の家族561人。その多くは、いまも社会に根深く残る差別をおそれ、匿名で参加している。
UPDATE
7月9日、ハンセン病家族訴訟で、安倍晋三首相が控訴しないことを表明した。国の賠償を命じた熊本地裁判決が確定する。
首相は「筆舌に尽くしがたい経験をされたご家族のご苦労をこれ以上長引かせるわけにはいかない」とコメントしている。
UPDATE
6月28日、熊本地裁は国の責任を認め、賠償を命じる判決を言い渡した。

ハンセン病。日本には、たった20余年前まで存在した「らい予防法」に基づき、この病にかかった患者たちを、無理やりに社会から隔離した歴史がある。
多くは家族の元を引き離され、塀に囲まれた隔離施設に収容された。死ぬまでその中で暮らし続けないといけない運命を、国に決められた。
強制的に患者を収容する運動なども全国的に広まり、社会に差別や偏見は広がった。そのため多くの人たちは、病が治ったとしても、園の中で暮らさざるを得なかった。
病を理由に中絶や断種をさせられる夫婦たちもいた。国の「ハンセン病問題に関する検証会議」の最終報告書によると、1949年から96年までハンセン病を理由に不妊手術をされた男女は1551人。堕胎手術の数は、7696件に及ぶ。
こうした隔離政策は、「らい予防法」が廃止される1996年まで続いた。そして、その隠れた被害を受けてきたのが、患者たちの家族だった。
親と引き離されて暮らさざるをえなかった、近所や学校でいじめを受けた、結婚が破談になった、就職や進学を諦めたーー。自死に追いやられた人も、いる。
そんな家族たちは2016年、「国の誤った隔離政策で社会に根付いた偏見」によって差別されたとして、熊本地裁に初めて、集団訴訟を起こしたのだ。
そもそも、なぜ家族なのか

そもそも、ハンセン病をめぐっては、元患者に対しては国が謝罪し、補償を続けている。
これは、「らい予防法」が廃止された5年後の2001年、元患者が起こした集団訴訟で、隔離政策の違憲性が認められたからだ。
熊本地裁での判決では、遅くとも1960年以降、治療薬「プロミン」の普及などから隔離政策は必要性がなく、違法だったと指摘している。
一方、今回の裁判の原告は、患者が発症当時に同居していた家族や、患者の子どもたちだ。1人当たり500万円の損害賠償に加え、名誉回復のため新聞紙上への謝罪広告の掲載を求めている。
原告の数は当初は59人だったが、最終的に561人になった。その多くは、いまも社会に残る偏見や差別をおそれ、顔も名前も伏せて裁判に参加している。
いまも、差別が残っているなんてーー。そう疑問に思う人もいるかもしれない。しかし、いまも残っているっているのが、現実だ。
私は朝日新聞記者だったころ、ある原告に取材をしたことがある。
30代の男性原告は、父親が療養所の入所者だったことから、交際していた女性との結婚が破断した、という過去を明かしてくれた。父の病は治っているにも関わらず、だ。
父親のことを告げたとき、女性本人は受け入れた。しかし、その両親には、こんな言葉を投げかけられたという。「娘に病気がうつる。どう責任を取るんだ」「家の近くに来るな」
「つながり」を取り戻すために

「いまも、自分の肉親がハンセン病だったことを言えない、という現実が残っています。私たちが家族たちの声に、そして社会としてその責任とどう向き合うか、問われている裁判なんです」
そうBuzzFeed Newsの取材に語るのは、これまで、60人の家族たちに聞き取りを続けてきた東北学院大学准教授(社会学)の黒坂愛衣さんだ。
『ハンセン病家族たちの物語』を上梓しており、今回の裁判では専門家証人として、法廷で証言台にも立った。
「国は、隔離政策をやっていく中で、ハンセン病が怖いものだと宣伝をしてきた。その影響は家族にあったんです」
「らい予防法が家族に影響を与えていたということをきちんと認めて、謝罪をきちんとするということが必要だと思っています」
黒坂さんは裁判に当たって、さまざまな原告たちの声を聞いてきた。
小さい頃で親と引き離され、本当の親を「お父さんと呼べない」と語る人。親が収容されるときに家を真っ白に消毒され、いじめられた、という人。自分が再び入所したとき、妻が心を病み、子どもを残して命を絶ってしまった、という人。
語られることのなかった「悲劇」が、今回の裁判をきっかけに明らかになった、という。そしてこの裁判は、そうした家族たちが「つながり」を取り戻すものでもあるのだ、と。
「生まれること自体を否定されていた」
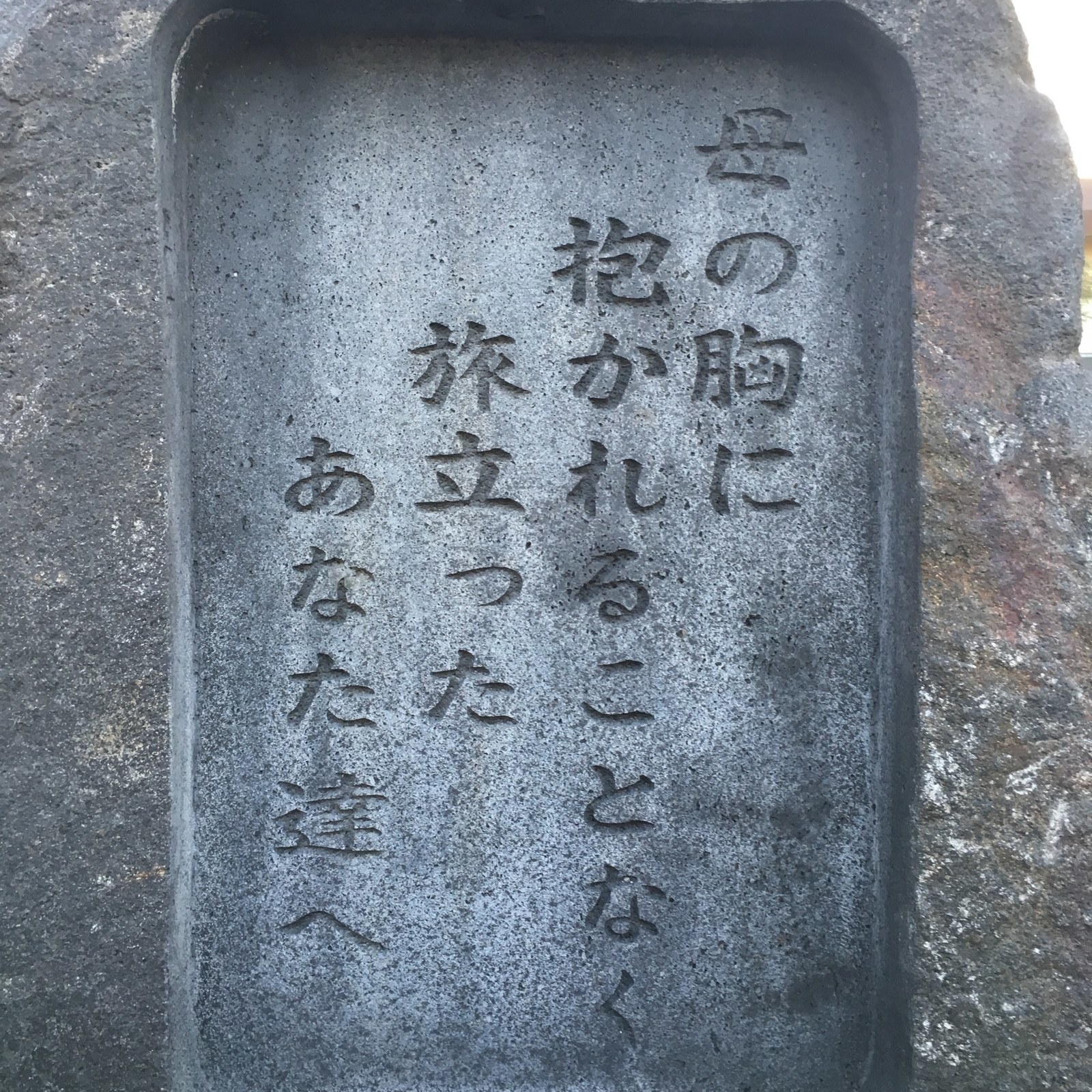
障害者が堕胎を強いられていた「優生保護法」には、ハンセン病の患者たちも含まれていた。
この法律の条文には、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と記されている。これに基づき、「らい病」(ハンセン病)や障害を抱えた人たちの堕胎が行われ、多くの命が奪われたのだ。
ハンセン病の場合、「ホルマリン漬け」にされて標本にされた子どもたちが、各地の療養所で見つかっている。6施設で100体以上にのぼった。
今回の裁判では、そうした政策下で母親が中絶手術を受けたが、奇跡的に生まれてきた、という原告もいる。
聞き取りにはこう語っていたそうだ。「そもそも生まれること自体を否定をされていたことが、ショックだった」と。
黒坂さんはこうも語る。
「療養所で堕胎手術に携わっていたある看護師は、『当然だと思っていた』と語っています。国がもちろん法律をつくったということもありますが、市民が当たり前のものとして、その優生主義に乗っかっていたんです」
「国の責任を問うことは大切なこと。でも、そうした私たちの責任を、突きつけられる裁判なのだと思っています。そしてそれが、過去の問題ではなくて今も続いていることをどうしていくのかは、社会の側にかかっているんです」
判決は6月28日、午後2時に下される予定だ。
