好きな本ばかりが並んだ自分の本棚。背表紙を指でなぞりながら、ふと手が止まった。
「大好きな物語を、疑わなきゃいけないんじゃないか」
小説家・彩瀬まるさんが、5年間あたためてきた構想を、最新作『森があふれる』(河出書房新社)につなげたきっかけだった。
ある日、妻が発芽した

『森があふれる』は、男性作家・埜渡徹也をとりまく人物の視点で構成されている。埜渡は、妻の琉生(るい)との関係をモデルにした恋愛小説が出世作となっていた。
無垢で、いたいけで、セックスを主体的に楽しむ女性として描かれた"妻"に、男女問わず多くの読者が惹かれ、実在の妻もこんな感じなのかと想像をめぐらせていた。
しかし、琉生は夫の不倫を知り、植物の種を大量に飲んで倒れてしまう。翌日、琉生の全身の毛穴から緑色の芽が吹き出す。蔓や根が急速に伸び、やがて家を飲み込む森へと成長していく。
妻が発芽して森になる。そんなおぞましい設定は、なぜ生まれたのだろうか。
「妻が突然キレて発芽するという設定は、5年ほど前から書きたいと思っていたんです。いままでも夫の作品の苗床になっていたんだから、いまさら植物の苗床になっても構わない、とやけになる流れで。ただ、これを長編にできると感じたのは、ここ数年の間に世の中にうねりが起きたからです」
モデルの告白が「加害者性」に気づかせた

2017年にアメリカで起きた#MeToo のムーブメントは日本にも波及し、性暴力被害の告発が次々と起きた。
なかでも彩瀬さんに衝撃を与えたのは、写真家の荒木経惟さんのモデルを16年つとめていたKaoRiさんの告白だったという。
2018年4月、KaoRiさんは「モデルとして尊重されていなかった。報酬のないヌード撮影を強要され、待遇の交渉すらできなかった」などとして、荒木さんとの関係について綴った文章をnoteに掲載。BuzzFeed Newsの取材には、こう話していた。
「『アラーキーのミューズ』としての自分と、本当の自分との間で、引き裂かれそうになっていた。自分より、写真の中の自分のほうが価値があるのではないか。そんな感覚にずっととらわれていた」
写真によって奪われ続けてきたというKaoRiさんの訴えを知ったとき、彩瀬さんは「自分も加害者だったのでは」と感じたのだと振り返る。
それまで、多くのヌード写真を興味深く鑑賞し、荒木さんの写真展に足を運んだこともあった。
よほど親しい関係でなければ目にしないような、すべてを露わにした写真の数々。美しいと感じるだけでなく、こんなふうに芸術のために人を説得して脱がせることができるのは、写真家の力量なのだと感じていたという。
「目の前ですごく過激なことが起きているけれども、モデルは同意しているはずだという安易で平穏な想像をして、自分にとってショックの少ない物語を無意識のうちに作っていたのでしょう」

著名な芸術家の前で、女性は自発的にすべてを露わにし、多くの人が感動する作品づくりに貢献する。その構図があること自体を否定するわけではないけれど、なぜひとかけらの疑問を持たず、女性は自ら望んだはずだと思えていたのだろう。
「KaoRiさんの告白によって、都合のいい物語を用意していた自分も、加害者の一人だったのではないか、と気づいたんです」
彩瀬さんは、自分が心を動かされた作品ばかりが並んでいる本棚を改めて見直した。同意のないセックスの描写がある物語があった。最終的に「でもいいの、こうなることを待ってたの」と現実を受け入れる登場人物の女性。
作者は何らかの意図があって、そのようなフォローの言葉を登場人物に言わせているはずだ。そして自分は、そのシチュエーションに疑いを持たず、この物語を良いと思ってきた。
「その性を性愛の対象にしている人間がつくった理想の像と、生身の人間との間に乖離があることに気づかない、あるいは見過ごしてきた私自身も、偏見を内面化していたんじゃないか。それは、差別に加担してきたのと同じではないか。そういうことが気になるようになったんです」
そのファンタジーは誰のためのものか

直木賞候補となった短編集『くちなし』には、不倫相手の左腕と暮らす女性や、蛇になって愛する男を食べる女性が登場する。空想の世界の描写を得意とするからこそ、彩瀬さんはファンタジーを突き詰めていく。
なぜ作者はそのファンタジーを書こうと思ったのか。そのファンタジーは誰のためのものなのか。読者はそのファンタジーから何を感じ取るのか。
「結局、表現の自由ということにまるっと入ってしまうんですよね。どうせファンタジーなんだから、真に受けるべきじゃない。特定のユーザーに向けられた表現なんだからこれでいい。それはその通りです」
「でも、その表現がどんな考え方から出てきたものなのか、なにかしらの思いこみに囚われていないか、検討する習慣をもつことは大切だと思います」
さまざまな像が入り乱れる
例えば、女性は男性よりも神秘的であるとか、直感的であるとか、子どもを産んだらホルモンのはたらきとは別の母性という特別な包容力が生まれるとか、そうした描きかたについて。
「そうした作品は昔からたくさんありましたし、女性とはそういうものなんだ、自分もそういうものなんだ、とおそらく小学生のころにはもう無批判に受け入れていました。でも、現実的で、経験重視で、母性よりも理性で子育てしている人の魅力も、より描かれるようになるといいのではないでしょうか」
「女性の体は女性のものだけど、女性の"像"は公共のもの。そして像には表現の自由があります。ただ、その像があまりに一方向に『女性とはこういうものである』と補強されたり、語る力をもつ人によって強調されたりすると、像のほうが生身に影響を与えてくる可能性があります」
「ある人が好む像があったら、『私はこっちの像のほうがいいと思う』『私ならこんな像を表現したい』と語りが入り乱れるのが、きっと一番いいんですよね」

『森があふれる』の登場人物は、さまざまな"像"に縛られている。よき母親、よき娘、よき嫁の像であったり、理不尽な待遇にも甘んじるサラリーマン像であったり。他人から規定された像だけでなく、自身に内面化された像もある。
登場人物がおかしさを自覚していないことは、自覚していない視点のままで書かれている。だから物語は、読み手の想像力に委ねられた状態で進んでいく。
なぜ、あえてもつれをほどかなかったのか。
「単純に誰かを悪者にするのではなく、細かくこんがらがったことを、こんがらがったまま書きたいと思っていました。私自身が、言語化できないモヤモヤを抱えてきたせいかもしれません」
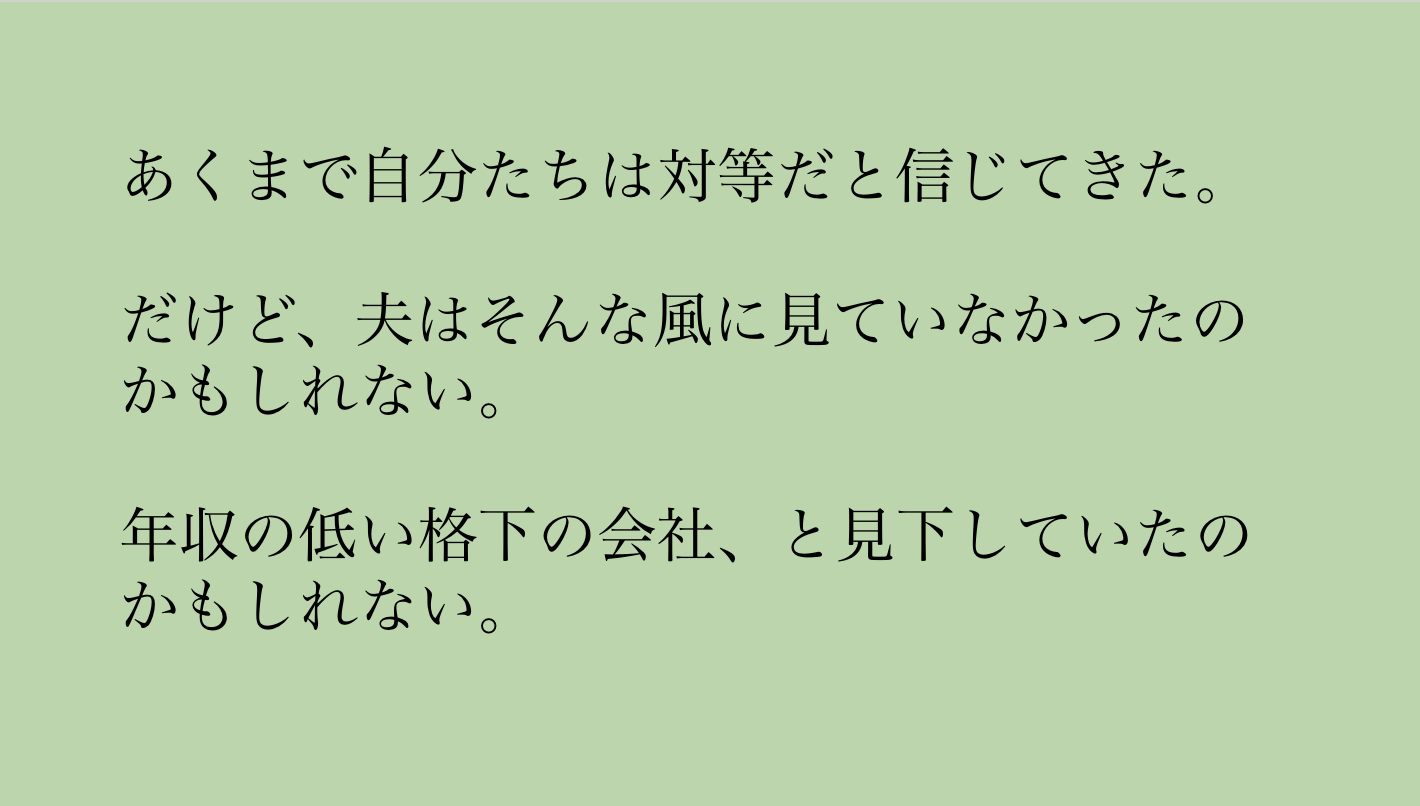
自分自身にもある固定観念
彩瀬さんは15歳のときに母親を亡くしている。たまに顔を合わせる親族は、「男は仕事、女は家庭」が当たり前だった世代。大学を卒業し、就職した彩瀬さんに「数年後には辞めて家庭に入り、跡取りを産むべきだ」と繰り返し言っていた。
「お前しかいないんだから頼りにしているぞ、と後継的なポジションを要求しながら、最終的には私ではなく、未来の私の夫と子どもを頼りにしているようでした。ふわふわとしたすべてを押し付けられ、それに応えなきゃというプレッシャーがあった。当時はその正体がわからず、ずっとモヤモヤしていたんです」
「単純に誰かが悪いといって解決するものでもない。固定観念は周りから与えられるだけでなく、忖度をしてきた自分自身にもあるものですから。そんな入り組んだ感じを思い出しながら書いていました」
目の前の相手に愛おしさを感じるなら
どうすれば、そのモヤモヤから抜け出せるのか。『森があふれる』には複数の夫婦が登場する。すれ違ったままの夫婦もいれば、対話の糸口を見出した夫婦もいる。
登場人物のひとり、編集者の瀬木口は、家庭をとても大切なものだと感じている。ある日、妻子が姿を消すが、残された手紙を読んでもなお、瀬木口には妻がなぜ出て行ったのかがわからない。
「なぜ相手を傷つけてしまったのか、指摘されればわかるけれど、言われないと認識する機会が訪れないということはよくあります。認識の機会がなかったから残酷なことをするのは、性別に関係なく、あらゆる差別がそうだと思います」
「認識していなかったことを責めて終わってはいけない。目の前の人間に何かしらの愛おしさを感じるのなら、相手はきっと受け取ってくれるはずだと信頼して、球を投げ続けていく必要があるのです」
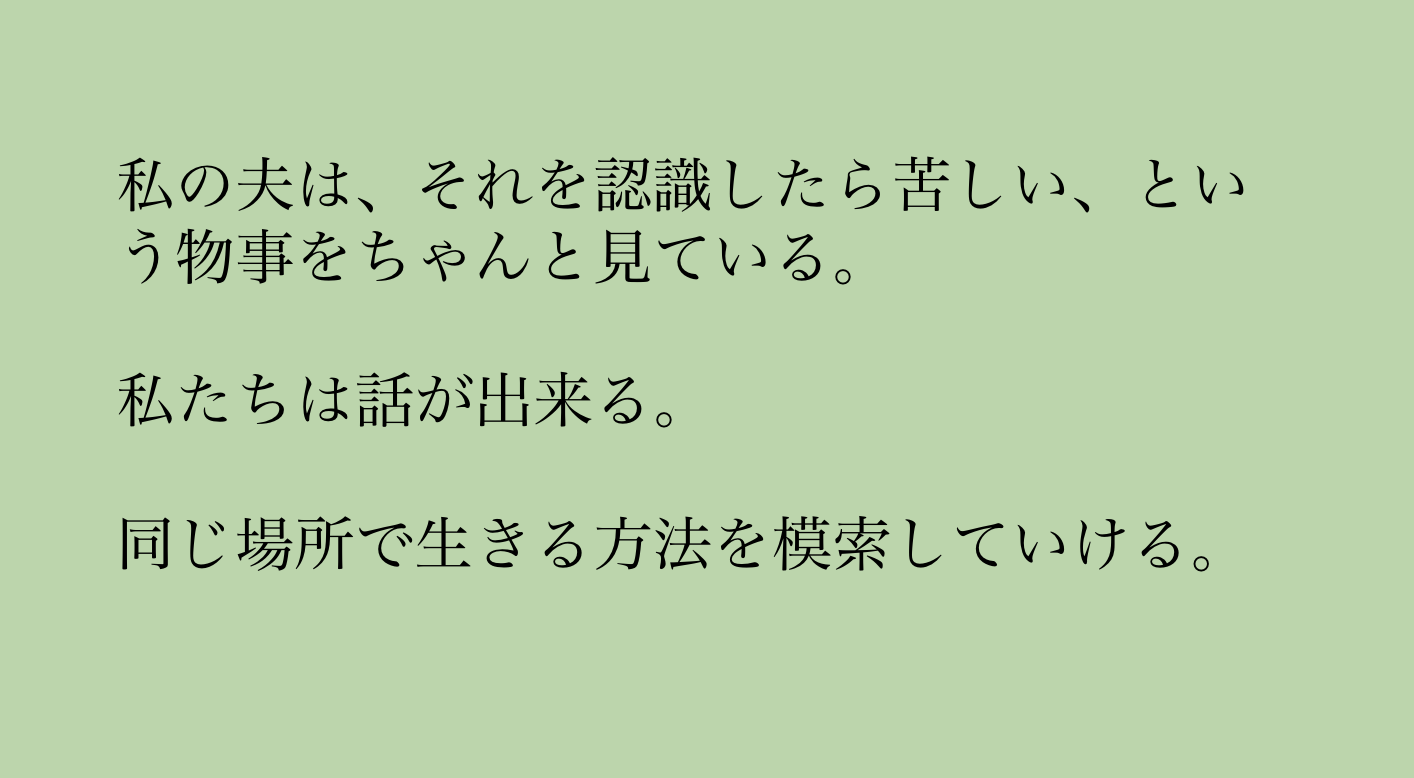
ファンタジーとリアルの乖離が生み出すもの
彩瀬さんは男性の登場人物の視点を描くときに、自分がかつて、自分自身や周りの女性に対して持った覚えがある偏見を散りばめ、言語化した。
「こんなひどいことを見ました、では小説にはなりません。なぜそんなひどいことをするに至ったかは、自分に近いほどわかる気がするので、内面から出た暴力性を中心に書きました。『あなたたちもこういう考え方をしているんでしょう』という、私の男性に対する偏見をさらけ出すことにもなるので、とても怖い作業でした」
「もし『男のことを書けていない作家だよね』と言われたら、そこからやっと議論が始まるじゃないですか。ステレオタイプな女性像に対して『私は神秘的でも、直感的でも、母性のかたまりでもない』という意見が出てはじめて議論が始まるのと同じように、小説を読んで『俺はこんな考え方はしない』という批評が出てくることは、生身の男性と、男性の像が理解されていくうえで、きっといいことなのではないかと思います」
小説の登場人物たちの視点は、それぞれ決して「正しい」ものではない。だからこそ、ファンタジーとリアルの乖離が、対話につながるといい。
小説家・彩瀬まるさんが目指したファンタジーの狙いは、そこにある。

